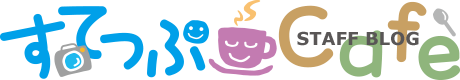2014年9月28日の東京新聞より。ゴリラ一色の研究人生を送ってきた山極寿一(やまぎわじゅいち)さんが、来月、京都大学長に就任する。その山極さんにアフリカの森でゴリラから教わった山極流「幸福論」を語ってもらったインタビュー記事です。家族を大切にし、みんなが対等に生きる。そんな「人間らしさ」はゴリラにもあるそうです。
2014年9月28日の東京新聞より。ゴリラ一色の研究人生を送ってきた山極寿一(やまぎわじゅいち)さんが、来月、京都大学長に就任する。その山極さんにアフリカの森でゴリラから教わった山極流「幸福論」を語ってもらったインタビュー記事です。家族を大切にし、みんなが対等に生きる。そんな「人間らしさ」はゴリラにもあるそうです。
・人間の社会はゴリラに似た部分があったのに、ニホンザルの方に近づいている。
・多くの人は、ゴリラが胸をたたくドラミングを、拳でたたく宣戦布告と思っている。実際は手のひらでたたいていて、宣戦布告ではなく自己主張。
・人間は本来「勝ちたい」のではなく「負けず嫌い」なんですよ。
興味深いインタビューで「なるほど~」とうなずける言葉がたくさんありました。今回も、頑張って全文入力していますので、興味を持った方は、是非読んでみてください。
なぜ霊長類学を選んだのですか。
京大理学部に入学したころ学部を超えた人類学研究会というのがあって、上野千鶴子さん、嘉田由紀子さんたちがいた。そこに生意気にも参加して、人類学が私に合うと感じました。その人類学を理学部でやるのが霊長類学です。人を知るためにはサルを知ることが大切。人間は、人間でない動物から進化をしてきた。その姿を知らなければ人間やその社会の由来はわからないからです。
ニホンザルの研究を始めたころ、屋久島で初めて純粋な野生の猿を見ました。餌付けされたサルは人間にこびたり、体形も太めだったりする。でも野生のサルは本当に美しい。人間になんか全く関心がない。野生のサルを見ないとだめだなと思いました。
ゴリラの研究に入ったきっかけは。
1970年代は類人猿研究が開花した時期でした。76年にコンゴ(旧ザイール)にまだ知られていない大きな群れがいるとわかり、2年後、26歳で初めて野生のゴリラに出合いました。まだ未熟で十分な観察ができず、ゴリラに襲われたこともありました。その後、ゴリラ研究の先駆者の米国人女性ダイアン・フォッシーさんがルワンダやウガンダにまたがるヴィルンガ火山群で開いたフィールドで、本格的にゴリラ研究を始めました。
どういう着眼点で研究をするのでしょうか。
今西錦司さんは「サルには歴史を書く能力がない。おまえたち研究者がサルになり代わって、群れに入って、サルの歴史を書け」と言いました。単に見ているだけでなくサルになってみるんです。自分は人間で、サルのように行動すると矛盾が出てくる。そこに発見がある。体が資本で、無理もします。暗くなって帰り道がわかんない。でもここまで追ってきたんだから、もうちょっと追ってみようかなと思う。そうすると面白い発見が現れるんです。
命の危険もあります。目の前の人が毒蛇にかまれて死んだこともあります。でも、本来人間もそういう中で進化してきたんだから生きられないはずはない。ゴリラはここで生きているんだから、俺が生きられないはずはないという安心感もありました。
ゴリラの群れに仲間として入れましたか。
ゴリラと同じように行動しました。ゴリラは体が大きいから動きが遅い。その速度で動いて、ゴリラの声を出す。体の構造が違うから同じ声は出せませんが、一生懸命まねをすると、こいつはちょっと変なゴリラだなと思ってくれます。
マウンテンゴリラと一緒に雨宿りをしたこともあります。ハゲニアという大木の空洞に私一人でいっぱいのところへ、6歳のタイタスといういたずら小僧のゴリラがやってきて「ンー」ってのぞき込んで、体をねじ込んできた。俺が入っているって「オッホ」って言ったけどだめで、80キロくらいある体で私の膝の上にのって、私に覆いかぶさり、あごを私の肩の上にのせて寝始めたんです。
心臓の鼓動を感じる。手を握ると、毛ばっかりかと思ったら骨太で腕が太い。手や顔を触った。顔の皮膚って真っ黒なんだけど柔らかいんです。手がすごく熱い。汗をかいている。まつげがすごく長かった。
ゴリラの何が見えてきましたか。
多くの人は、ゴリラが胸をたたくドラミングを、拳でたたく宣戦布告と思っている。実際は手のひらでたたいていて、宣戦布告ではなく自己主張。あの行動には二重性があって、自己主張しているけれど、誰かがなだめに来てくれれば矛を収めると伝えています。人間のような演技性がゴリラにはあるんです。
二者択一では収拾がつかない事態に、間に入ってくれる仲裁者が必要だから、ゴリラは群れをつくる。仲裁者は強くないメスでも子どもでもいい。それはニホンザルとは全く違う社会です。ニホンザルは強い弱いを決めていて、弱者が強者に譲れば争いは起きない。だけどゴリラは負けない。強い弱いを認め合わない。
理性が野獣と人間を分けるといわれますが、そういうものがゴリラにもあるのでしょうか。
最近「『サル化』する人間社会」という本を書きました。人間の社会はゴリラに似た部分があったのに、ニホンザルの方に近づいています。勝敗にこだわるようになった。その方がトラブルが長引かなくて時間がかからず経済的だからです。
でも人間は本来「勝ちたい」のではなく「負けず嫌い」なんですよ。現代社会は両者を混同しています。負けないという思想のゴールは、相手と対等になること。ゴリラと同じです。一方で勝つことは相手を屈服させるから、恨みが残り、相手は離れていく。本来人間は勝敗を先送りして、対等な関係を保ってきたんじゃないか、経済より社会が重要だと言いたいんです。
人間がサルと違うのは、社会や集団のために何かしたいと思えること。そこに自分が加わっている幸福感が、いろんな行動に駆り立ててきたんです。サルは自分の利益を最大化するために集団をつくります。今は人間も自分の利益を増やしてくれる仲間を選び、それができなくなったら仲間はいらない、となっています。
人間とゴリラは五感がほとんど変わりません。そういう五感を中心につくられる社会には、それほど大きな差はないと思います。ゴリラの群れは十頭前後で、これを共鳴集団というんですが、人間でも家族やスポーツチームがこれにあたります。仲間の癖、性格を心得ているから、試合に出れば、声はかけるけれど言葉は交わさない。何を求めているか、目配せでわかる。
われわれは家族や、家族のように親しく接している人との共鳴集団があることで安らぎや幸福感を得ていると思います。私はこれから、そういう人間の家族の起源を再考し、理論に残したいと思っています。
京大学長になられます。文科省は大学に国際競争力を求めています。経済性が重視される時代に、どうやって山極流の運営をしていくのでしょうか。
国際競争力を高めて、日本は本当に豊かになるでしょうか。逆に今の日本は内向きになっています。日本の国力や経済力だけを高めて周辺諸国を圧迫したら、日本は孤立しちゃいます。
日本人はどんどん海外に出るべきだし、海外の優秀な人も日本に来てほしい。海外と戦うなんて意識をもたず、きちんと交流して国際人を育てたい。学問には国境がないから、日本と外国という対立関係をつくってはだめ。いろんな国から集まって新しいことを考える、そういう先駆けになれればいいですね。